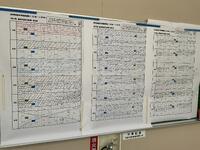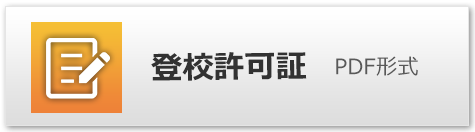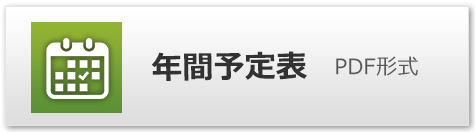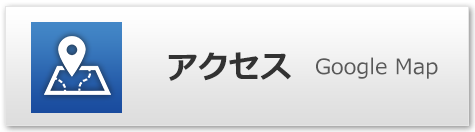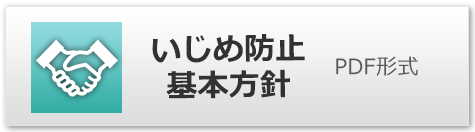文字
背景
行間
学校からの連絡
修学旅行3日目
2月13日(金)、2年生の修学旅行は最終日を迎えました。
この日はクラスで清水寺と三十三間堂を見学しました。
清水寺では、快晴の空のもと、有名な舞台から京都の街並みを一望しました。これまで事前学習や班別活動の準備を重ねてきた生徒たちにとって、その景色は特別なものとなり、仲間とともに過ごした時間を振り返りながら、思い思いに見入っている姿が印象的でした。
三十三間堂では、整然と並ぶ1001体の仏像の迫力に圧倒されながら、日本の歴史や文化の奥深さを実感しました。実際に自分の目で見て、空気を感じる体験を通して、学びがより確かなものになったことと思います。
3日間の行程を通して、生徒たちは仲間と協力し、時間やきまりを守りながら行動する中で大きく成長しました。今回の修学旅行で得た学びと経験を、これからの学校生活へと生かしていくことを期待しています。
修学旅行2日目
2月12日(木)、2年生の修学旅行では班別タクシー研修を行いました。
伏見稲荷、二条城、京都タワー、金閣寺、平安神宮、北野天満宮など、生徒たちは事前の話し合いをもとに自分たちで計画した見学地を巡り、主体的に学びを深めました。
現地では互いに協力しながら熱心に見学する姿が見られ、教室では得られない貴重な経験となりました。天候にも恵まれ、体調を崩す生徒もなく、全員が元気に充実した時間を過ごすことができています。
修学旅行1日目
2月11日(水)から13日(金)までの3日間、2年生が関西方面への修学旅行に出発しています。
1日目は奈良を訪れ、東大寺の大仏を見学するとともに、広大な奈良公園を散策しました。歴史ある文化財や豊かな自然に直接触れ、生徒たちは多くの学びを得ている様子です。
これまで実行委員を中心に仲間と話し合いを重ね、準備を進めてきました。2年生にとっての集大成となる修学旅行が、かけがえのない思い出となり、一人一人の大きな成長の機会となることを願っています。
綾子舞伝承学習終了式
3日(火)、綾子舞伝承学習終了式を厳かに執り行いました。
当日はご多用の中、近藤教育長様にご来校いただき、児童・生徒のこれまでの努力をねぎらうとともに、今後への大きな励みとなる温かいお言葉を頂戴しました。続いて行われた代表児童生徒による感想発表では、綾子舞に向き合ってきた日々の学びや成長が率直な言葉で語られ、会場は深い感動に包まれました。記念品の授与の後には、綾子舞保存振興会の坂井会長様から、心のこもった感謝のお言葉をいただき、新道小学校・南中学校の児童生徒にとって、まさに大きな節目となる意義深い式となりました。
綾子舞は、500年という長い歴史を誇る、地域のかけがえのない文化です。この伝統が今日まで脈々と受け継がれてきた背景には、地域の皆様の熱意と尽力があります。今後も、地域と学校が一体となり、この貴重な文化を次の世代へ確かに継承していってほしいと願っています。
指導者の皆様には、今年度も熱心かつ丁寧なご指導を賜り、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。来年度もどうぞよろしくお願いいたします。
後期期末テスト終了
3日(火)に後期期末テストが無事終了しました。
テスト前から「学習強調週間」と位置づけて取り組んできましたが、その期間中には2学年の学年閉鎖という困難な状況もありました。それにもかかわらず、生徒たちは気持ちを切らすことなく、日々の学習に真剣に、そして粘り強く向き合う姿を見せてくれました。
学校全体が学習に集中する雰囲気に包まれたのは、強調週間を丁寧に計画・運営してくれた学年委員の皆さんの力によるものです。生徒一人一人の意欲を引き出し、前向きな空気をつくってくれたことに心から感謝します。ありがとうございました。
トイレ改修工事完了
9月より校舎および体育館のトイレ改修工事を行ってきましたが、先週末に工事が無事に完了しました。
暑い日も寒い日も私たちのために工事を行ってくれた業者の方へ、代表生徒がお礼を伝えました。
感謝の気持ちを忘れずに、新しいトイレを大切に使っていきます。
基礎学力テスト(数学)
16日(金)、第3回数学基礎学力テストが行われました。
この日に向けて、昼休みの学習教室に自主的に参加したり、休み時間に仲間と励まし合い、教え合いながら学習に取り組んだりする姿が見られました。
目標に向かって努力する皆さんの姿は、本当に素晴らしかったです。
令和8年のスタート
新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
8日(木)より冬休みが明け、学校生活が再びスタートしました。久しぶりに登校した生徒たちの表情からは、新しい年への期待や、これから始まる学校生活への意欲が感じられました。
休業後集会では、2名の代表生徒が登壇し、新年を迎えての決意や、これからの学校生活に向けた目標について、堂々とした態度で発表しました。それぞれの言葉には、自分自身を見つめ直し、よりよい学校生活を送りたいという前向きな思いが込められていました。
また、校長講話では「自分を磨くための新年の抱負を立てよう」というテーマのもと、一日一日の積み重ねの大切さや、目標をもって行動することの意義について話がありました。
後期後半がいよいよスタートし、今年度も終わりに近づいています。これまでの学校生活を振り返りながら、一人ひとりが自分なりの目標をもち、残りの期間を大切に過ごしてほしいと思います。
生徒たちが充実した学校生活を送り、心身ともに成長できるよう、教職員一同、引き続き支援してまいります。
休業前集会
23日(火)に、休業前集会が行われました。
はじめに各種表彰が行われ、その後、来年度の会長・副会長・団長の認証式を行いました。会長からは、来年度に向けた力強い決意表明がありました。
続いて、2名の代表生徒から、これまでの取組を振り返っての発表がありました。
校長講話では、12月に実施した人権に関する授業や人権講演会を振り返りながら、「差別やいやがらせはなぜ起こるのか」というテーマについてお話がありました。
これから冬休みが始まります。
健康や安全に十分気をつけながら、思い出に残る充実した日々を過ごしてほしいと思います。
休業明けに、新年の元気な姿で再び会えることを楽しみにしています。
どうぞ、よいお年をお迎えください。
人権講演会
19日(金)、人権講演会を開催し、講師の方から大変貴重なお話を伺いました。
講演では、差別の存在、人を深く傷つけてしまう「差別の怖さ」について、具体的な事例を交えながらお話いただきました。
今回の講演をきっかけに、教育活動の中で一人ひとりが人権意識を高めていきます。