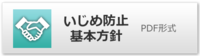2021年12月の記事一覧
生徒会役員選挙 立会演説会・投票
本日の5,6限に生徒会役員選挙の立会演説会と投票が行われました。
全校生徒は49名ですが、会長に2名、副会長男子に3名、女子に3名、応援団長1名が立候補する大変積極的な役員選挙となりました。
生徒には、「生徒会は民主主義を学ぶ場であり、みんなで地域社会を運営することを体験してほしい。「みんなで」とは、一人一人全員ということで、つまり「私が」ということです。ただ、全員が違う意見をもつことになるので、そこでは「話合い」が必要です。「私が」と「話合い」が「みんなで」の意味です。」と述べました。
演説の後の質疑は40分ほどかかる熱のこもったものとなりました。
最後に、選挙管理委員会の担当教諭が、「多様な意見が出ることが集団の進化には大切」と述べつつ、「投票は選択肢を絞ることになる。投票の重みを理解して考え、決めてほしい」と全体に声を掛けました。
その後、投票。本年度は、自分が決めた候補者の名前をそれぞれが書くように変わり、生徒は慎重に名前を書いていました。
人権教育、同和教育授業③
先週金曜日に各学年で人権教育、同和教育授業を行いました。
いずれも「生きるⅣ」を読んでの授業です。
1年生は、部落差別による差別・偏見について、2年生は部落差別による結婚差別の問題を、3年生ば部落差別による就職差別の問題を考えました。
1年生は、そこから自分自身の中の差別心に目を向け、どうすればそうした差別がなくなるのかを考えました。
資料を読み、その状況について考える際に、想像力をもち、ときに自分自身に置き換えて考えることが大切です。
問題を自分のこととして捉えることにつながります。
自分を大切にし、そして自分以外の人も大切にできる感性を育みたいと思います。
対話による存在の承認~全校朝会
本日の全校朝会では、いくつかの表彰(賞状伝達)の後に、生徒に対話を行ってもらいました。
一つ目の話題は、好きなことや好きなものです。
ペアを組み、自分の好きなことを30秒ほど話し、相手が質問をします。
その後、互いの話の共通点や似ているところを探ってもらいます。
聞いてみると「小さい頃から好きだった」と答えてくれたペアがありました。
次に、自分がどんな学校にいたいか、お互いの思いを話してもらいました。
これも同様に、共通点を探ってもらいます。
同様に聞いてみると、3年生の一人は「一人一人を尊重できる学校」と答えてくれました。
対話は、まず相手の話を聞き、相手の考えを理解することです。
もちろん完全には理解できませんから、分からないところを質問したり自分の理解を確認したりして、相手の考えをより的確に理解していこうとすることが必要です。
そうした過程で、自分自身が相手に受け止めてもらったという安心感を得ることができます。
このことを西研先生は一昨日紹介した本の中で、「存在の承認」と述べていました。
今回はさらに、共通点を探り合ってもらいました。
この過程が入ると、「相手と共通な想い」があることに気づき、「みんなの中の一人」という感覚が生まれるそうです。
今日のような活動を通して、学校に対話の文化が広まることを期待しています。
中学生人権作文の表彰
本日の昼休みに、全国中学生人権作文コンテスト柏崎地区大会の表彰を行っていただきました。
柏崎人権擁護委員協議会長の宇佐美様と人権擁護委員の神林様にお出でいただき、直接お渡しいただきました。
入賞した二人は、ともに1年生です。
神林様からは、7月に人権週間の折に全校生徒向けに人権に関する講話をいただいています。
作文には生徒が思いを率直に述べていて感心したと感想を述べていらっしゃいました。
自分の考えを述べ、それが認められることも自分や自分たちの自信を深める一つですね。
私もうれしくなりました。
水球全日本代表 志水祐介選手の講演会②
先日行われた志水選手の講演会に関わり、付け加えです。
先日の演題は、「夢を実現させるために ~挫折を乗り越える方法~」でした。
東京医科大学哲学教室教授の西研先生は、「しあわせの哲学」(NHK出版)の中で、「キルケゴールは、人はいつも『これからの自分はこのようにできるはず』という『可能性』を信じることによって生きている、と述べている」と説明しています。
そして、西研先生は、この可能性を「生の可能性」と呼び、具体的には、「『したい・かつ・できる』という確信のこと」としています。
さらに、この「生の可能性」をさらに詳しく述べ、具体的に次の三つを挙げています。
①「親しい人たちとの関係」~「自分のことを受け入れてくれているし、自分もその人たちのことが好きである。そうした関わりは、人が生きるうえで重要な「生の可能性」であり、喜びの源泉になりうる」
②「社会的な活動」~「自らのエネルギーを夢中になって発揮して何かの形にしていくことは、充実感につながります。」
③「趣味や楽しみ」~「打ち込んでいる趣味だけでなく、お気に入りのカフェで読書する、というようなささやかな楽しみも人にはあります。」
そして、「三つのうち、自分が生きるうえでどこに重きを置いているか、ということは人によって違」い、「そして、どんな人も、重要な『可能性』だけでなく、ささやかな『可能性』ももっていて、それらすべてによって生きている」と説明しています。
西研先生の仰っていることを志水選手のお話に当てはめると、水球は志水選手にとって、①②③いずれにも当てはまるものです。そう考えると例えば、勉強は②で、ギターは③と分けられる場合もあると思いますが、人によっては仕事が三つのうちの二つに該当したり、その時々により③と関係したり①と関係したりとなることもあるのかもしれません。
そして、きっと一つの活動が①②③の中の複数に関係するもののほうが、より「生の可能性」たるものになるように感じます。
そう考えると学校は、学習や部活動などができるだけ①~③のいずれにも当てはまるようなものになるよう工夫する必要があるのでしょう。