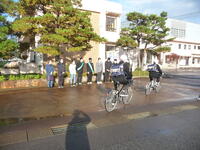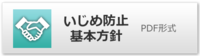学校生活の様子
休業前集会
明日から冬休みです。本日は、休業前集会を行いました。
部活動や美術作品、数研、人権作文学校表彰等の表彰に続き、4名の生徒に他の生徒への発表がありました。
1年生は、SDGsをこれから大切にして取り組んでいきたいと。
2年生は、家庭学習をしっかりやっていきたい、部活動も精一杯取り組みたいと。
3年生は、受験勉強への取組の決意。
生徒会からは、スライドを使いながら行事の振り返りが分かりやすく説明されました。
その後、校長の話として、北中ミーティングの話題としてとったアンケートの集約。
その他、昨日は3年生が、今日は2年生がレクを行うなど、生徒も良い思い出になったと思います。
人権作文学校表彰
一昨日、法務局の方と人権擁護委員の方にお出でいただき、人権作文に関わる学校全体の取組を表彰していただきました。
5年間の人権作文への参加者数が多かったためです。
原稿用紙は3枚以上ですが、5枚びっしりと書く生徒も少なくありません。
本年度は、市内で3校が学校表彰を受けたとのこと。
継続するのは、何事も難しいことですから、こうして表彰していただくのは、生徒にとっても職員にとっても励みになります。
ありがとうございました。
1年生での公開研究~栄養バランスの良い朝食
先週の金曜日に1年生で保健体育の公開授業を行いました。
「栄養バランスの良い朝食を食べよう」というタイトルです。
保健体育の担当に加え、栄養教諭と養護教諭が入り、3人でのティーム・ティーチングです。
おにぎりだけの朝食Aと、トーストとオレンジジュースの朝食Bを見ながら意見を出し合い、栄養バランスがより良い朝食を考えました。
グループごとに話し合い、鮭をプラスするなどの案が提案されました。
こうした実生活に直結した学習は、生徒にとっても意欲のわく、本当に大切な授業です。
栄養教諭や養護教諭が入ることで、説得力が増し、生徒もさらにやる気をもって取り組んでいました。
学校保健委員会での健康委員会
本日の放課後、学校保健委員会を行いました。
タイトルは、「勉強できる食事について」です。
講師に柏崎市福祉保健部健康福祉課の佐藤佳誉子様をお迎えして、講話をいただきました。
参加者は、PTA保健環境部の方々と、生徒会の健康委員会の生徒、そして関係職員です。
当校の給食の残量や睡眠時間の様子を確認後、佐藤様より、大変分かりやすく、そしてためになるお話をいただきました。
「おやつは、お菓子でなく、補食です。」
「コーラに入っている糖分は3gのスティックシュガー19本分で、しかも液糖ですぐに血糖値が上がる。」
「バランスの良い食事を摂ることが大切」
お話の後、健康委員会の生徒は、学年ごとに掲示板に貼るポスターを作り始め、3年生は早速完成していました。
私自身も大変勉強になりました。
講師の佐藤様、本当にありがとうございました。
新学力検査の実施
昨日本校では、1,2年生で新学力検査を行いました。
国語、社会、数学、理科、英語の5教科です。
柏崎市全体でほぼ同時期に実施しているものです。
こちらのテストは、新学習指導要領がより強く反映されており、思考力や判断力、表現力が確認される問題が多いのが特徴です。
当校では、ふだんから課題を解決する学習を各教科で実施しています。
もちろん話し合ったり発表し合ったりする場面が用意されます。
この中で新学習指導要領で強調されている思考力等も伸びてきています。
また、来週の火曜日には、実力テストを行いますので、これと併せて生徒はテスト勉強を今月行ってきました。
これらのテストを通じて自分の力を高め、確認し、今後に生かしてほしいと思います。
写真は、先日3年生で行った人権教育、同和教育の2時間目の授業の様子です。グループを生かした学習です。
3年生面接練習・バスケットボール部
先日、3年生で面接練習を行いました。
今後の受検の中で面接を行う生徒もいますし、行わない生徒もいます。
しかし、受検に向けた心構えをつくること、そして、義務教育を終え、社会人に向かう一歩となる卒業に向けてマナーを身につけることをねらいとして、全員で学習を行っています。
全員で行う中で、次第に姿勢や挨拶が整っていきました。
これを一つの契機として、社会への目を育ててほしいと思います。
写真は、バスケットボール部が先日地区大会を勝ち抜いたときのものです。
生徒会三役認証式・生徒朝会
本日の生徒朝会では、最初に、先日決まった新三役の認証式を行いました。
生徒会長、副会長男女、応援団長です。
認証書を受け取る際の返事に、これからの1年間への決意を感じました。
その後の生徒朝会では、応援団により、当校伝統のよさこいについてのクイズが行われました。
・いつから北条中学校ではよさこいを踊り始めましたか。
・それはどの地震がきっかけでしたか。
など、よさこいを受け継いでいく誇りを感じさせるクイズでした。
3年生から1,2年生に学校を引き継いでいく上での、下級生への期待が込められているのだと思います。
写真は、初めの2枚が認証式、最後の1枚が応援団によるクイズです。
3年生数学公開授業
本日、柏崎刈羽の学校教育研究会での公開授業を数学で行いました。
図形に関する発展的な内容です。
なかなか答えが見つからず、生徒は、グループで話し合いながら、課題を追求し続けました。
最初は、堅い雰囲気だったのが、課題に没頭する中でだんだんと熱が入っていきます。
こうじゃないか、いやこう考えた方が良いんじゃないかという発言が続きます。
課題を追求しても答えが見えてこない、そんなときにも追求し続ける姿がそこにはありました。
今求められる、粘り強く探究する力です。
澄み切った青空の今日、心に残る1時間を過ごすことができました。
音楽部アンサンブルコンテスト、バスケットボール部地区大会
先週の土曜日は、音楽部が上越文化会館でアンサンブルコンテストに、バスケットボール部が新人上越地区大会出場しました。
音楽部は、北条中から2グループが出場、管楽5重奏と木管打楽器4重奏です。
夏に比べてどの楽器も美しい音色を奏でるようになっていて、全員が練習に打ち込んだのがよく分かりました。
終わってから声を掛けると、「終わった~」「緊張した」という声と共に、やりきったという表情が見えます。
まさに「青春」です。
バスケットボール部の試合の様子は残念ながら見ることができませんでした。
本日話を聞くと、すばらしい試合を行い、新人柏刈大会がなくなった悔しさの中で練習を続けた成果を発揮することができたとのことです。
今朝は、どことなく誇らしげな様子での登校でした。
写真は音楽部のみ、バスケ部は、残念ながら用意できず、すみません。
びっくりゲストインタビュー・球根植え付け
昨日より給食時にびっくりゲストインタビューを広報委員会が行っています。
冬休みのことやクリスマスのことをインタビューするのですが、インタビューされる人はそのときまで分からないというもの。
ランチルームでの給食ならではの活動です。
一方、整備委員会が昨日、冬の晴れ間を縫って、来春に向けて正門の花壇やプランターに球根を植えました。
下の写真は、インタビューの様子と球根の植え付けの様子です。
3年生修学旅行のまとめ発表会
本日の1限に3年生は修学旅行で学んだことについて紹介し合う発表会を行いました。
コロナ禍により当初の予定が変わり続けた3年生でしたが、それぞれが旅行を通して自分の中に新たな発見を感じ、他の生徒にしっかりと伝えていました。
お店の方やバスガイドさんから挨拶の大切さを学び、早速実践している生徒。
新潟の魅力に気付き、この地に生まれたことに誇りをもって生きていきたいと述べる生徒。
洋食器をつくる職人の方の技術の高さに心を打たれ、自分も丁寧に行っていきたいと考えた生徒。
新潟の食のおいしさに気付き、その後の給食も味わいが変わった生徒。
相手に気を配ることの大切さに気付いた生徒。
様々な感想に旅行を通して大きな思い出や学びがあったことが感じられました。
最後に担任が、どこに行っても楽しみ、感動することができる生徒達の感性のすばらしさを讃えるとともに、ぜひその感性を大切にしてほしいと話しました。
私も同感です。一つ一つに感動し、みんなで楽しむことができる北条の生徒に本当に感心した修学旅行。2ヶ月が経ちますが、今尚、心温まる姿として印象深く残っています。
校則について生徒会本部が検討!
一昨日になりますが、生徒会専門委員会が行われました。
当校は、全員が専門委員会に所属していますので、この時間は全員が活動します。
その中で生徒会本部が校則についての検討を始めました。
先月の全校朝会の中で話したことを受けて、生徒会が動いてくれたことをまずは嬉しく思います。
本部では、全校朝会で出たことについて、本部としての意見をまとめています。
頭髪や服装、その他、様々な内容について考えてくれました。
こうした活動を通して、学校で大切にしたいことを全員で考え、絞り込んでいくことができると思います。
写真は、広報委員会と風紀委員会です。
生徒会役員選挙 立会演説会・投票
本日の5,6限に生徒会役員選挙の立会演説会と投票が行われました。
全校生徒は49名ですが、会長に2名、副会長男子に3名、女子に3名、応援団長1名が立候補する大変積極的な役員選挙となりました。
生徒には、「生徒会は民主主義を学ぶ場であり、みんなで地域社会を運営することを体験してほしい。「みんなで」とは、一人一人全員ということで、つまり「私が」ということです。ただ、全員が違う意見をもつことになるので、そこでは「話合い」が必要です。「私が」と「話合い」が「みんなで」の意味です。」と述べました。
演説の後の質疑は40分ほどかかる熱のこもったものとなりました。
最後に、選挙管理委員会の担当教諭が、「多様な意見が出ることが集団の進化には大切」と述べつつ、「投票は選択肢を絞ることになる。投票の重みを理解して考え、決めてほしい」と全体に声を掛けました。
その後、投票。本年度は、自分が決めた候補者の名前をそれぞれが書くように変わり、生徒は慎重に名前を書いていました。
人権教育、同和教育授業③
先週金曜日に各学年で人権教育、同和教育授業を行いました。
いずれも「生きるⅣ」を読んでの授業です。
1年生は、部落差別による差別・偏見について、2年生は部落差別による結婚差別の問題を、3年生ば部落差別による就職差別の問題を考えました。
1年生は、そこから自分自身の中の差別心に目を向け、どうすればそうした差別がなくなるのかを考えました。
資料を読み、その状況について考える際に、想像力をもち、ときに自分自身に置き換えて考えることが大切です。
問題を自分のこととして捉えることにつながります。
自分を大切にし、そして自分以外の人も大切にできる感性を育みたいと思います。
対話による存在の承認~全校朝会
本日の全校朝会では、いくつかの表彰(賞状伝達)の後に、生徒に対話を行ってもらいました。
一つ目の話題は、好きなことや好きなものです。
ペアを組み、自分の好きなことを30秒ほど話し、相手が質問をします。
その後、互いの話の共通点や似ているところを探ってもらいます。
聞いてみると「小さい頃から好きだった」と答えてくれたペアがありました。
次に、自分がどんな学校にいたいか、お互いの思いを話してもらいました。
これも同様に、共通点を探ってもらいます。
同様に聞いてみると、3年生の一人は「一人一人を尊重できる学校」と答えてくれました。
対話は、まず相手の話を聞き、相手の考えを理解することです。
もちろん完全には理解できませんから、分からないところを質問したり自分の理解を確認したりして、相手の考えをより的確に理解していこうとすることが必要です。
そうした過程で、自分自身が相手に受け止めてもらったという安心感を得ることができます。
このことを西研先生は一昨日紹介した本の中で、「存在の承認」と述べていました。
今回はさらに、共通点を探り合ってもらいました。
この過程が入ると、「相手と共通な想い」があることに気づき、「みんなの中の一人」という感覚が生まれるそうです。
今日のような活動を通して、学校に対話の文化が広まることを期待しています。
中学生人権作文の表彰
本日の昼休みに、全国中学生人権作文コンテスト柏崎地区大会の表彰を行っていただきました。
柏崎人権擁護委員協議会長の宇佐美様と人権擁護委員の神林様にお出でいただき、直接お渡しいただきました。
入賞した二人は、ともに1年生です。
神林様からは、7月に人権週間の折に全校生徒向けに人権に関する講話をいただいています。
作文には生徒が思いを率直に述べていて感心したと感想を述べていらっしゃいました。
自分の考えを述べ、それが認められることも自分や自分たちの自信を深める一つですね。
私もうれしくなりました。
水球全日本代表 志水祐介選手の講演会②
先日行われた志水選手の講演会に関わり、付け加えです。
先日の演題は、「夢を実現させるために ~挫折を乗り越える方法~」でした。
東京医科大学哲学教室教授の西研先生は、「しあわせの哲学」(NHK出版)の中で、「キルケゴールは、人はいつも『これからの自分はこのようにできるはず』という『可能性』を信じることによって生きている、と述べている」と説明しています。
そして、西研先生は、この可能性を「生の可能性」と呼び、具体的には、「『したい・かつ・できる』という確信のこと」としています。
さらに、この「生の可能性」をさらに詳しく述べ、具体的に次の三つを挙げています。
①「親しい人たちとの関係」~「自分のことを受け入れてくれているし、自分もその人たちのことが好きである。そうした関わりは、人が生きるうえで重要な「生の可能性」であり、喜びの源泉になりうる」
②「社会的な活動」~「自らのエネルギーを夢中になって発揮して何かの形にしていくことは、充実感につながります。」
③「趣味や楽しみ」~「打ち込んでいる趣味だけでなく、お気に入りのカフェで読書する、というようなささやかな楽しみも人にはあります。」
そして、「三つのうち、自分が生きるうえでどこに重きを置いているか、ということは人によって違」い、「そして、どんな人も、重要な『可能性』だけでなく、ささやかな『可能性』ももっていて、それらすべてによって生きている」と説明しています。
西研先生の仰っていることを志水選手のお話に当てはめると、水球は志水選手にとって、①②③いずれにも当てはまるものです。そう考えると例えば、勉強は②で、ギターは③と分けられる場合もあると思いますが、人によっては仕事が三つのうちの二つに該当したり、その時々により③と関係したり①と関係したりとなることもあるのかもしれません。
そして、きっと一つの活動が①②③の中の複数に関係するもののほうが、より「生の可能性」たるものになるように感じます。
そう考えると学校は、学習や部活動などができるだけ①~③のいずれにも当てはまるようなものになるよう工夫する必要があるのでしょう。
国語のディベート紹介
今月も今日が最後となります。
日が経ちましたが、今月10日に行った公開授業の国語の学習を紹介します。
3年生でディベートを行っています。
論題は、生徒と共に話し合ったもので、「75歳以上は自動車免許を返納すべきである」について、是か非か。
ポイントは三つです。
①一人一役。
肯定派と否定派がそれぞれ4名ずつ、司会と記録、タイムキーバーをそれぞれ聴衆が担い、15名全員に役割があります。
②iPadと電子黒板を使った根拠の提示。
目で見ての資料論題に対し、肯定派も否定派もインターネット等から資料を用意して立論等を行い、質疑へと移りました。その際、資料をiPadから電子黒板に移して説明をしていたので、質問や反駁の際もその資料を提示してもらいながら行うことができていました。これまでのディベートが互いの意見をメモにとるのみで行っていたのに対し、メモに加えて目で見ての資料があることが互いの理解を促し、意見交換を活発にさせていました。
③対立で終えずに、それを止揚する考えへ。
当日は、ディベートでしたが、次時には、「この問題の本質は何だろう。そこから問いを考えてみよう」と投げかけ、「どうしたら事故を防げるか」という問いについて話し合い、「技術開発をさらに進めるべき」「高齢者講習の内容を改善すべき」などの意見が出て、話合いを終えたそうです。ディベートを通して問題を浮き彫りにし、それを止揚するより良い考えを探る授業です。
生徒会役員選挙の選挙運動開始
先週の金曜日に、生徒会役員選挙の立候補が締め切られ、本日より選挙運動が始まっています。
朝、登校する全校生徒に向けて、自分への投票を呼び掛けています。
昼休みは、ランチルームで立候補者が公約を順に説明していきます。
(3年生は現在会議室で食事をしていますので、Zoomで配信した映像を視聴しました。)
先日の衆議院選挙の若者の投票率が低かった対策として、中学校や高校の生徒会の在り方が鍵を握るという意見があります。
もっともな意見で、学校で生徒会があるのは、民主主義を学ぶためです。
そして、どの学校も生徒会活動を教育活動としてしっかりと行い、生徒会選挙も適切に運営されているはずです。
もちろん、投票率はほぼ100%ですし、無効票も少ないはずです。
しかし、上記のような課題が改善されずにあることを、多分全ての中高の教員は残念に思っているはずです。
その中で、ではどんな工夫が考えられるか。
一つには、生徒が学校の教育活動に関わる部分を増やしていくことだろうと思います。
簡単に言えば、生徒の意見を大切にするということです。
生徒の全ての考えにイエスということはできないかもしれませんが、まず耳を傾けて話し合うことは少なくとも必要だろうと思います。
これも、これまでずっと行ってきたことなのかもしれません。
ただ、何か変えなければという思いがあります。
その中で、自分たちの学校を自分たちがつくる、つくった、という思いを少しでももつことができたなら、少しずつ変わるのではないかと思い、今回の生徒会役員選挙に期待しているところです。
薬物濫用防止教室
本日の6限に薬物濫用防止教室を行いました。
柏崎ライオンズクラブのお二人を講師にお招きしての学習です。
2,3年生はランチルームにて、1年生は教室でオンラインにてお話をお聞きしました。
お話の中で柏崎でも薬物の検挙が意外に多いことに生徒は驚いていました。
動画では、SNSで知り合った男性から体調が良くなるアプリをもらい、その後、覚醒剤をもらうようになり依存していく女子高校生が描かれていました。
生徒は怖いなという気持ちを感じたことと思います。
最後に、「ダメ 絶対」をみんなで声を合わせて誓って、学習を終了しました。
柏崎ライオンズクラブの皆様、ありがとうございました。
水球全日本代表 志水祐介選手の講演会
本日の5,6限は、1学年PTAで、リオオリンピックの水球日本男子チームのキャプテンで、7月の東京オリンピックにも主力として出場した志水祐介選手をお招きして講演会を行いました。
全校生徒が参加し、志水選手の明るく前向きなお人柄の、力あるお話に触れさせていただきました。
中学校を卒業する際に、全日本代表になってオリンピックに出ると書いたことを実現するため、精一杯進んできたとのこと。
「努力すれば夢は実現する」のでなく、「叶うまで努力するから夢が叶う」とのお話など、夢を実現させるための具体的な方法を教えて下さいました。
実際に、ウォーターポロクラブ柏崎で教員やラーメン屋さんでのお仕事をしながら朝と晩に練習を行っていたことや、けがで諦めかけたときのお話など、順風満帆でない水球人生の中で、まさに決してあきらめずに夢を求めてきたお話でした。
どの生徒も憧れのような気持ちで志水選手を見ていたのではないかと思います。
お話のあと、一人一人にサインを書きながら写真を渡してくださる中で、生徒はどんどん志水選手に近づいていきました。
さらに各学級にも訪れて写真撮影に応じてくださったり、肩車をして下さったりするとても気さくなお人柄にどの生徒も心をつかまれていました。
本日ご講演をいただいた志水選手に心から感謝申し上げます。また、これからの更なるご活躍を北条中の生徒職員一同お祈りいたします。
6年生部活動体験
本日の放課後に、北条小の6年生が当校の部活動を体験しました。
初めに、部活動の紹介(北条中は、音楽部、文化部、女子バスケットボール部、野球部)を各部の部長が行いました。
緊張している様子でしたが、それぞれが自分たちの部活に入ってほしいという気持ちで精一杯話をしていました。
その後、グループに分かれての体験。
野球部では、当校の2年生が6年生にキャッチボールでのグラブの使い方を教えると、「なるほど。分かりやすい!」との声。
終わってからの感想を聞くと、「音楽部」がおもしろそう、との声も。
部活動の位置付けには、最近様々な意見がありますが、熱中したり充実感を得たりできる場としての力はやはりあります。
今日の部活動体験をとおして、中学校の部活をやってみたいな、楽しそうだなと思ってもらえるとうれしいと思います。
3年生確認テスト他
本日は、3年生が確認テスト(実力テスト)を行いました。
現在のそれぞれの入試に関わる学習の状況を確認するためのテストです。
素直で明るい北条中学校の生徒である3年生のみんなも、学習のことや進路のことを話すことが増えました。
11月の終わりになってずいぶんと入試を意識した雰囲気になっています。
入試で学習指導要領にある学力の全てを計ることは難しいかもしれません。
自分の中の違う面をみてほしい生徒もいるでしょう。
大切なのは、進路選択という場としっかりと向き合い、その中で自分の在り方を探り決定していくことと思います。
自分が思っていることを見つめ、回りの意見も聞きながら、自分の考えや思いを調整し、判断していくこと。
人生は課題の連続です。
進路選択という課題を通して、一歩ずつ成長していってほしいと思います。
写真は、本日の3年生の様子と、iPadを利用した生徒会誌作成の打合せ、そして北条の山々です。
鎌倉幕府の成立は何年か
「鎌倉幕府の成立は何年か」
いいくにつくろう鎌倉幕府、で1192年となるかと思いきや、実は、何をもって鎌倉幕府が成立したと言えるかは、難しい問題のようです。
この課題は、先日の職員研修で当校の社会科で1年生に投げかけられた問いでした。
この問いをもとに、生徒は、自分で考えると共に、グループでも考え、そして学級全員で話合いが行われました。
生徒は、問いを追究する中で、歴史的な認識を深めていくことになります。
こうした学習も探究的な授業です。
このような授業を日々行っていくことが今、求められています。
こんなわくわくする課題を考え、授業を行う職員を誇りに思います。
因みにこの社会の授業を行った職員の机上には様々な領域の書籍が積まれており、その中から生まれた問いです。
写真は、当日の社会科の授業と今日の赤い羽根共同募金の様月食月食です。
赤い羽根の共同募金
今週は、赤い羽根の共同募金を毎朝玄関で生徒会本部が呼び掛けています。
登校する仲間に掛ける声はどこかうれしそうで、毎日のように募金のお金を持ってくる生徒もいるようです。
隣で挨拶運動を風紀委員会が行っており、その生徒も混ざっての募金活動になっています。
職員も声を掛けられ、財布からお金を出して玄関へ。
天気も良く、楽しい朝が続いています。
定例生徒朝会
本日は、定例の生徒朝会が行われました。(月曜日は臨時生徒朝会)
初めに、生徒会長より玲瓏祭の振り返りと生徒会役員選挙に関わる話。
その後に、選挙管理委員会より本日公示された生徒会役員選挙についての連絡。
その中で、生徒会役員選挙を通して生徒会の意義を確認してほしいという話がありました。
「生徒会の意義」を生徒はどう考えているのだろう、さらに私たちはどう考えているのだろう。
先日の衆議院選挙での若者の投票率が低かったことを受け、中学校や高校での生徒会の役割を論じる方もいらっしゃいました。
そうした中で、改めて生徒会とは何なのか。
当校の校訓は「質実 自治 奉仕」とあり、「自治」はまさに生徒会を頭に置いた言葉でしょう。
戦後の北条の皆さんが当時の中学生や若者にどんな期待していたのかということに思いを馳せながら、今、生徒会の意義を再度考えてみる必要があると思います。
この後に行われた玲瓏祭のパフォーマンスの表彰を見て、さらに生徒会代議員会を経て決まった昼休みのカードゲームに関する連絡を聞いて、北条中の生徒会が生徒会の意義を体現しようとしているように思いつつ、さらに力ある生徒会になってほしいと感じました。
蓮池薫さん講演会&いじめ見逃しゼロスクール集会
本日の午前中、北条小学校で行われた蓮池薫さん講演会を、北条中生徒もズームにより各学級でお聞きしました。
新潟県主催「PTA対象拉致問題啓発セミナー」の一つです。
中央海岸で北朝鮮に拉致されたときの生々しい状況をお聞きするとともに、日本に戻ってきた際の経緯について教えていただきました。
ご講演を締めくくるにあたり、①今の問題であること ②拉致により夢や希望、何より自由を失われたこと ③北朝鮮のトップの方の行動を求めるのであって、一般の方々、特に在日の方を非難するのは間違っていること を知ってほしいと強くおっしゃっていました。
その後、蓮池さんは、中学校にもおいでくださり、各クラスを回り、生徒の質問に答えてくださいました。
・「帰ってきたときはどんな気持ちでしたか」~「子どもが北朝鮮にいる間は、気が気でなかった。しかし、子どもが日本に来てからは、やりたいことをやった。睡眠は3時間程度で勉強した。研究、探究はおもしろい。」
・「帰ってきたときに日本をどう思いましたか」~「日本は発展したなと思った。ただ、しばらくして人と人との関係が以前より薄れたようにも感じた。」
・「平和な未来をつくるにはどうすれば良いと思いますか」~国家間の外交が重要。
・「拉致問題の報道を見てどう思いますか」~横田めぐみさんを日本に帰したいと強く思っている。
各クラスで多くの質問が出たので、時間のために打ち切るほどでした。
拉致の事実をご本人から直接お聞きすることができたのは、生徒にとって大きな経験だったと思います。
こうした機会に恵まれたことに感謝します。
また、午後には、いじめ見逃しゼロスクール集会を小中合同で北条小学校体育館で行いました。
初めに小学校と中学校の各学年でのいじめ見逃しゼロに関わる取組を紹介。
その後、中学校の風紀委員会が考えた仲間同士でのトラブルの簡易的な劇を見て、何が問題なのかを小中合同グループで話し合いました。
顧問からは、生徒が試行錯誤しながら台本や資料を用意したとのこと。つくる過程でいろいろといじめについて考えたようです。本当によくがんばりました。
全ての生徒にとって居心地の良い、楽しく学ぶことができる学校をこれからも目指していきたいと思います。
生徒会役員選挙に向けて
本日は、生徒朝会が行われ、選挙管理委員会の運営で、生徒会役員選挙に向けて現役員から活動内容や期待する生徒像について、自分の経験を踏まえての説明がありました。
生徒会長は、学校の雰囲気や生活を左右する立場なので、責任を自覚して立候補してほしいと。
副会長男子、女子は、それぞれ体育祭か玲瓏祭の実行委員長のどちらかを担うことに触れ、計画的に準備を進める必要あると述べながら、
さらに、副会長女子は、この人と仲が良いからという理由で投票せずに演説などをもとに選んでほしい、
副会長男子は、選ぶ人たちもどんな学校になってほしいかを考えてほしい、
そして、応援団長は、的確に指示を出せたり、計画に行事を運営できたりする人に立候補してほしいと述べていました。
この後、質問が何人もの生徒からなされ、それに対して役員が的確に返答する姿は、さすが3年生という様子でした。
また、北条中学校が一歩前進しそうです。
二重の虹&保健授業&北条小さつまいもプレゼント
今朝は、急に強い雨が降り、生徒も自転車で登校するか困ったようです。
そんな中、校門に立って挨拶をしていると男子生徒が、「おはようございます。虹が見えます」と。
後ろを振り返ると、色の濃いきれいな虹が校舎にかかっています。しかも2重の虹です。
生徒はその虹をくぐるように登校していました。
本日はテストの二日目で、きっと昨晩の学習で疲れている上に、この雨でかわいそうになどと思っていた矢先の虹でした。
虹は、なぜか気持ちを明るくしてくれますね。
さて、先日の公開授業では、保健体育で「自然災害に備えて」(保健)が公開されました。
課題は、「私たちの北条中『災害緊急避難所』を作成しよう」です。
流れは、最初に避難所の写真を見せて課題を確認し、それが解決できるよう、北条中の校舎図に避難所の施設を書き込みながら避難所を計画するというものです。
探究型の学習であり、課題を解決する中で、生徒が学習内容を理解したり、身に付けたりしていきます。
その他の授業も、探究型の構成で学習が進みました。
探究は、総合的な学習の時間の時間の中でも行われますが、各教科の学習も探究をベースにしたものになることが現在求められ、それを具現化した授業だったと思います。
以上、先日の公開授業の紹介でした。
ところで、本日は、3年生の進路事務説明会が行われました。これを機に、一気に進学のムードが高まります。保護者の皆様、ご参加いただき、ありがとうございました。
さらに、北条小4年生が大事に育てたさつまいもを中学生に(職員にも!)プレゼントしてくれました。
大変おいしそうなさつまいもです。ありがとうございました。
後期中間テスト1日目
本日より後期中間テストが始まりました。
生徒の登校はいつもよりもそれぞれ5分くらい早いでしょうか。皆、テストに向けて緊張感があるようです。
先日、学校で大切な約束を生徒にアンケートで聞いたとき、派生して、テストについて書いている生徒がありました。
具体的には、テストを廃止してほしいというものです。
次の日に行った全校朝会で話し合った中で、その考えに対して意見を書いた生徒がありました。
・テストをなくしてしまうと自分の成績を確かめることができないので良くない。自分の間違えた問題を見直せない。
・テストがなければ、学習を積極的にする習慣が身につかないと思う。
といったものです。
それぞれ自分の学習を自己評価する場として、また一つの目標として、テストをとらえての意見です。
テストは、このように生徒自身が自分の力を確認するという目的がありますし、私たち教員にとっても、授業の評価や今後の生徒の支援を行う目的があります。
いずれにしても生徒の学習状況を教員が評価し、生徒自身も自分の学習状況を理解する場は必要です。
その際、テストは、明確さ、わかりやすさという点で有効な方法です。
全国には、定期テストをなくし、全て単元テストにしている中学校もありますが、テストを実施している点では同じです。
とはいえ、テストが嫌だと思う生徒の気持ちも分かります。覚えなければならないというプレッシャー、決まった時間の中で解かなければならない状況への緊張は強いでしょう。
さらに、自分の学習を評価されるということが、自分自身を評価されるということにも感じられ、共に学ぶ仲間と比較されるように感じる面もあるかもしれません。
本来は、学習は自分の可能性を広げるものですので、テストが嫌なために学ぶ楽しさが阻害されているとしたら残念なことです。
できるだけそうならないように、テストの意味を十分に伝えることや、生徒それぞれの学習状況を教員、生徒がともに確認できる適切な内容のテストにしていくこと、言い換えると、これまでの学習が確実に生き、振り返りができるもの、そして次の学習に意欲がわいてくるようなテストにしていく必要があるのだろうと思います。
写真は、今日のテストの様子です。
雨の合間の虹&市教委訪問
雨が続き、急に冬が近づいてきた感がありますが、そんな中の虹です。
校舎(体育館)の横に見え、カメラを取りに行くと残念ながらずいぶん薄く短くなっていました。
さて、本日は、柏崎市教育委員会のお二人の指導主事の先生にお出でいただき、授業公開と協議会を行いました。
授業については、国語、社会、英語、保体のどの授業も探究的な問いを立て、学習が進みました。
さらに、iPadや電子黒板などを生徒や教員が使いながらの授業で、生徒のいつも通りの意欲的な様子でした。
授業については、今後詳しく掲載していきます。
下の写真は、虹(校舎の横に薄く見えますか?)と協議会です。
小中合同避難訓練
本日は、北条小学校と連携して避難訓練を行いました。
北条小学校と北条中学校は併設の校舎ですので、どちらかに火災が発生すると、どちらの校舎も非常ベルが鳴ります。
本年度は、小学校で火災が発生した設定で訓練を行いました。
非常ベルが鳴った後、小中の教務室で連絡をとり、小学校での火災であることを確認して避難を指示しました。
小さなことですが、小中の大切な連携の場面です。
生徒には、柏崎市消防本部の管轄である柏崎、刈羽、出雲崎で発生している火災が昨年より多いこと、今年の1月に火災が5件発生していることを伝え、学校や家庭での注意を促しました。
写真は、1年生から3年生までの生徒(男子・女子)と職員が一緒にバスケットボールを楽しむ昼休みの様子です。
総合的な学習の時間について
2年生の本年度の総合的な学習の時間前半は、起業学習をテーマとして進めています。
雰囲気としては、国語や数学などの教科同様で、「起業科」といって良いほどの内容です。
ただ、国語や理科などの教科よりも大変実践的な学習で、グループで考えた会社を毎回より具体的な形にしていく中で、会社の基本を学ぶように進められています。
aisaさんがワークブックを作り、授業も進めてくださっていますが、実によくできた学びの場で、いつも感心して参観しています。
先週は、自分たちの会社をビジネスモデルカードに反映させる学習でした。
今回もそうでしたが、この起業学習で繰り返し立ち返るのは、会社のミッションであり、社会に対する自分たちのビジョンです。
そこから改めて思ったのは、学校は何のためにあるのかという学校のミッションを私たち教職員がどれだけ自覚しているかといことです。そして、学校を通して社会で実現したい私たち教職員のビジョンをもっているのかということです。
つまり、学校の存在意義です。
これからの社会では、会社やチームが自分たちのパーパス(存在意義)をどれだけ自覚しているかが重要とのこと。
本の中で読んでいたことを目の前で示していただいたように思いました。
学校外の方から、私たち教職員が教わることの多いのも、総合的な学習の時間です。
2年生性に関する指導&新ALT授業
少し前になりますが、2日(火)に2年生で性に関する指導を行いました。
柏崎市の事業により、助産師の方よりお出でいただき、外部講師としてお話しいただきました。
内容は、第2次性徴、受精から出産までの胎児の成長、そして命のつながりです。
事前のアンケートでは、やはり性についての情報をインターネット等から得ている生徒が多く、命の誕生に直接関わっている方からお話しいただくのは貴重で意義深いものです。
性教育は命教育です。
今回の授業を通して、自分が生きていることを命の繋がりの中で感じることができた生徒も多かったと思います。
1,3年生も今後性の指導を行っていきます。
また、今日は新しいALTが来校し、早速各学年で1時間ずつ授業に入りました。
誠実で親しみのある人柄から、生徒もたくさんの質問をしていました。
英語力向上を促す場が今後は毎週設定されます。大変楽しみです。
写真は、英語の授業と挨拶運動の最終日の様子です。
学校で一番大切なことは
一昨日の朝、全校集会があり、学校で一番大切なことは何だと思うか、全校で考えました。
前日に採ったアンケート「全校で守る約束を一つだけ作るとしたら、どんなものが良いと思いますか」の結果をもとに全校で考えました。
この意図は、「学校で一番大切なことは何か」ということでしたが、「きまり」として、服装や持ち物、テスト期間のことなどの意見を書いた生徒も多くいました。
生徒の率直な意見ですので、それも掲載し、生徒会で検討するよう促しました。
一方、学校で一番大切なこととしては、時間を守ることや、公共物に関することに加えて、挨拶をすること、いじめをせず助け合うこと、楽しく過ごすことなどがアンケートに挙がりました。
全校集会で、この中からもっとも大切だと思うことを選んでもらうと、良い関係であることと楽しく過ごすことを選んだ生徒が多くいました。
どの生徒もしっかり考えていて、ふざけた意見は一つもありません。
この姿勢が嬉しいですし、自分の考えを出し合い、話し合うことは、とても大切なことだと思います。
お互いの考えを出し合い、その理由を確認することで、目の前のことが違って見えてくると思います。
生徒の皆さんは、いかがでしたか。
写真は、今日の小中連携挨拶運動です。参加いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。
小中連携挨拶運動
今週は、本年度2回目の小中連携挨拶運動が行われています。
中学生は、中学校の校門と小学校の校門に分かれて、挨拶を行っています。
小学生は、昼休みに中学校に来て(校舎がつながっています!)元気よく中学生に挨拶をしています。
本日は、PTAの育成部の方々からも参加いただき、爽やかな朝の挨拶を交わすことができました。
いろいろな方から学校に入っていただけるのは、本当にありがたいことです。
コロナ禍で、地域の方やPTAの方との生徒の交流に難しい面がありますが、その中でもこうした活動を行えるのは、本当にありがたいことです。
音楽部引退コンサート
昨日(10/31)音楽部が当校体育館で引退コンサートを催し、ご家族の方や、卒業生、当校の生徒や職員など50名ほど参観者がある中、とても楽しい演奏を聴かせてくれました。
音楽部の生徒は4月から、週休日に1日練習を行ったり、外部講師の先生にもお出でいただいたりと、生徒は懸命に練習についてきましたし、目標をもって取り組みました。
その中で着実に上達し、コンクールや玲瓏祭などで自信をもって演奏するようになったと思います。
昨日の引退コンサートでは、3年生の男子が曲に合わせてダンスを披露するなど、大変楽しい会となりました。
そして、音楽部の生徒は、充実した練習を行ってきたという思いと音楽を楽しんだ笑顔に溢れていました。
保護者の皆様にもたくさんのご支援をいただきました。心より感謝申し上げます。
マラソン記録会で懸命にラン!
本日の3限は全校体育として、マラソン記録会を行いました。
1年生から3年生まで、全員が3kmを走ります。
持久走の得意な生徒もいれば、不得意な生徒もいます。
今朝、少し雨があたりましたので、今日はマラソンないかな、と少しほっとしている様子の子もいました。(雨は上がりました!)
走り終わってから、これでずっと気にしていたのが終わって良かったと話す子もいました。しばらくの間、大きな課題だったようです。
そうした生徒も含め、皆、懸命に走り、自分の可能性を広げていました。
そして、午後は皆元気に活動している様子をみて、さすが中学生と感心しました。
本当にお疲れ様。今日は、ゆっくり休んでください。
1年生地域探検
1年生が総合的な学習の時間で、地域を探検しています。
本日は、グループごとに北条を散策し、体験したりインタビューしたりしながら調査活動を行いました。
北条は、歴史のある町で、城跡があるとともに神社仏閣も多く、八石山など自然も豊かなところですので、追究活動には大変適した地域です。
今日は、八石山に登山したり城山について教えていただいたり、普廣寺様を訪れて北条のお寺についてお聞きしたりしています。
生徒は、楽しみながら自分たちの生まれ育った地域を調べています。
玲瓏祭感想③&3年生確認テスト等
玲瓏祭の感想の続きです。
当校の玲瓏祭は、コンクール形式をとっていません。
各学年は1学級であり、学年間で競い合うのは難しいです(やはり3年生が上手です)から、当然と言えば当然かもしれません。
ただ、コンクール形式がない中で、どれだけできるかという問題が合唱発表にはあります。
果たして生徒は本気で歌えるのか、という問いです。
しかし、北条中学校の生徒は、コンクールでなくとも、精一杯の声を出し、美しい歌声を披露してくれました。
本当にうれしいことです。
さて、本日は3年生が確認テストを行っていました。その横で、2年生が数学の学習。
確認テストで良い点数をとることは、本来の学習の目的ではありませんが、目標の一つにはなりますし、今の3年生にとっては重要なテストです。
終了後は、各テストの様子について、みんなで語り合っていました。
玲瓏祭感想&人権教育、同和教育授業②
昨日は、玲瓏祭の振替休業日でお休み、そして火曜日の今日、生徒は元気に登校しました。
ところで、北条の子どもたちはなぜあれほど(玲瓏祭)の表現ができるのか。
もともとの子どもたちの力とも言えますし、地域がはぐくんでいるとも言えます。ずっと仲間でいる信頼感が生むのかもしれません。
いずれにしても、コントやダンス、楽器演奏等の発表を楽しい司会がつなぎ、会場を温かい雰囲気が包んだ1時間は、私にとって生涯忘れられない時間となりました。
さて、本日の5限の道徳の授業では、全学年で人権教育、同和教育に関する授業を行いました。
1年生は、新潟水俣病に関して、2年生は結婚差別の問題、3年生が被差別部落への偏見です。
いずれも教材をもとに話し合いながら差別の問題について考えました。
来月の小中合同いじめ見逃しゼロスクール集会にもつながる学習です。
玲瓏祭~個性で輝け~みんなが活躍できる 最高の舞台~
本日、北条中学校では玲瓏祭(文化祭)が行われました。
前半の合唱発表では、各学年の発表、そして全校生徒の合唱。
全校で綺麗に歌い上げる「虹」には涙がにじみました。
後半のパフォーマンスは、希望者による9グループの発表。
トップバッターの3年生によるコントで場が一気に和み、その後は、漫才やダンス、音楽発表などの発表が続きました。
どのグループも仕上がりのレベルが高く、表現力も豊かで、初めでの玲瓏祭に圧倒されました。
これだけのことができる子どもたちに驚いたと言っては失礼かもしませんが、どのグループもすばらしいパフォーマンスで、全国に誇る文化祭だったと思います。
今回の玲瓏祭のスローガンは、「個性で輝け~みんなが活躍できる 最高の舞台~」。本当に全員が活躍した玲瓏祭に万歳。
お出でいただいたご家族の皆様、ありがとうございました。
学級って何だろう?
今朝は、後期の正副級長任命式を行いました。
その後、「学級とは何だろう」と尋ね、生徒全員に考えてもらいました。
3人の生徒から考えを発表してもらい、「協力するところ」「一緒に学ぶ場」「助け合いを学ぶ場」などの意見をもらいました。
生徒からは、とても良い意見をもらったのですが、私の結論は、(当たり前のことですが)「一緒に勉強する集団」です。
「北条地区に住む12歳から14歳のみんなに、ここに来ると勉強ができるよ、と呼び掛け、それに対して「ようし、勉強できるんだ」と応えたみんながここに集まって中学校ができています。そして、年齢ごとにグループをつくっていて、その集団が学級です。」とまず説明しました。
その上で、「でも一緒に過ごす中でいろいろありますね。けんかをしたり、何かトラブルになったり。そんなときのために級長さんや副級長さんは、相談役になってほしい。そういうことがあったら声をかけてほしい。学級のお兄さん役、お姉さん役を務めてほしい。もちろん、その他のみんなもお互いに声を掛け合って、みんなが過ごしやすく楽しい学級にしていこう。」と話しました。
写真は、2年生の総合です。本日もaisaの水戸部さんからお出でいただきました。今日は、「収支を計算してみよう」です。
1年生演劇鑑賞教室
本日の午後は、柏崎市内の中学1年生がアルフォーレに集まり、演劇を鑑賞しました。
演目は、柏崎市出身の堀井真吾氏脚本・演出による舞踊劇「綾子舞物語」です。
市内の中高校生らが舞う綾子舞を挟みながら、鵜川に伝わる綾子舞伝承の物語を紡いだもので、コンパクトながらストーリー性十分の内容です。
生徒たちは、バス旅行のような雰囲気で行き帰りともとても楽しそうでした。
また、他校の生徒と集うことに少し興奮の様子も。
中学生のときに本物に触れる経験ができることは幸せなことです。
そして、コロナ禍の中、こうした経験がまたできるようになったことに感じ入った次第です。
玲瓏祭パフォーマンス中間発表②
本日も昼休みに玲瓏祭パフォーマンス中間発表が行われました。
まずは、1年生3人による漫才。ずいぶん練習を重ねたようです。少し声が小さかったのでもう一踏ん張りです。
続けて、1年生の別のグループによるコント。こちらもマイクを3本利用する一方で回線が2本しかないという難しさの中、スタッフと協力して調整していました。
最後に、2年生と3年生によるダンス。学年を超えたグループでの発表も楽しみです。
多目的室を覗くと、3年生男子がコントの練習を自主的に行っていました。
5限には合唱のリハーサルも行われています。
当日まであと2日の練習を残すのみとなりました。自分たちの最高を目指して、この時間を存分に楽しんでほしいと思います。
玲瓏祭の裏方も意欲的&小中合同いじめ見逃しゼロスクール集会の合同打合せ
玲瓏祭のパフォーマンスは、いくつかのグループが参加しますが、パフォーマンスに出るのはちょっと、という生徒もいます。
そうした生徒は、裏方を務めており、当日の音響等の係を行うこととなっています。また、当日にいたるまで、事前に出演者に必要物品を確認して、必要なものを揃えるなどの準備を行っています。
見ていると裏方の生徒がとても意欲的に活動を行っていることに感心します。
こうした係の生徒がいるからこそ、ステージの上で発表できる生徒がいます。
当日は、学校全体で玲瓏祭を盛り上げ、すばらしい日にしたいと思います。
また、本日昼休みに11月16日に行われる小中いじめ見逃しゼロスクール集会の打合せを小中合同で行います。
生徒会の風紀委員と本部の代表が出席します。
ここから既にいじめ見逃しゼロスクールが始まっています。
玲瓏祭パフォーマンス中間発表
今週末に行われる玲瓏祭に向けて練習や準備が本格化しています。
本日は、先週から続くパフォーマンス中間発表が昼休みに行われ、二つのグループが発表していました。
3年生二人による連弾。千本桜です!ボリューム感満点の迫力ある演奏でした。他に2曲演奏するとのことで、ドラムやチューバも入るとのこと。
そして、1年生二人によるダンスパフォーマンス。二人で練習を重ねた様子が見え、当日が楽しみにです。
本日は、以上の2グループでしたが、この中間発表会を生徒の実行委員会が運営し、当日がスムーズに流れるよう細かい点まで確認をしていました。
玲瓏祭が生徒による主体的な取組となっている一端を見ることができ、北条中生徒の力を感じました。
同じ体育館では、生徒会本部がスローガンを横看板に貼り付けていましたが、そこでも生徒会長が下級生に丁寧にやり方を教える様子があり、感心しました。
自分自身を表現することが、お互いの信頼関係の中で保障されていることをそれぞれの生徒が感じているからこその姿に思えました。今後もこうした雰囲気を大切にして日々の教育活動を行っていきたいと思います。
2年生起業学習&合唱中間発表
本日は、2~3限に2年生が総合的な学習の時間に起業学習を行いました。講師は、柏崎のNPO法人aisa理事長の水戸部 智 様です。
まず、前回の復習を兼ねて自分たちのグループで考えた事業についての確認。前回の初めに授業を参観したときは、どのグループも事業の具体化が進まず、困っていた様子でしたが、その後、かなりの進展があったようです。
農家の方による出荷物へのイラスト添付、リサイクル、売れなくなった商品の活用、eスポーツカフェなど。
どれも、社会のニーズを探りつつ、近隣には見当たらない内容となっていて、感心しました。
続けて、それぞれがグループの代表として、他のグループの生徒と1対1で事業を説明し合い、疑問や意見を交換しました。
学習のポイントとして、事業を考える際に、最初が「誰に」を生徒に考えるよう工夫してあり、相手への意識を持たせています。なるほどと思いました。
4限は、合唱の中間発表。2年生、1年生、3年生の順で発表し、最後に全校での合唱を練習しました。
当校の合唱発表は、コンクールではなく、あくまでも発表会で競争がありません。その中で生徒は、自分たちとして最高の合唱を目指して練習をしてきています。そのことを嬉しく思います。
玲瓏祭パフォーマンス練習
雨の日が続く中、今日は青空が広がり、とんぼがうれしそうに飛んでいます。
生徒は、今週に入って合唱とパフォーマンスの練習に懸命です。
パフォーマンスは、グループごとでのダンスや音楽、漫才、化学実験などのステージ発表です。
今年は、体育祭が2週間ほど延期されたこともあり、なかなか練習がままならず、生徒も焦っているようですが、楽しんで取り組んでいます。
後期の始業式には、「楽しくて、ためになる学校」をつくっていこうと呼び掛けました。ぜひ、みんなで玲瓏祭を楽しんでほしいと思いますし、楽しむ中でこそつかむものもたくさんあるはずです。
写真で玲瓏祭のスローガンを紹介します。大好きなスローガンです。
生徒朝会~プロジェクトを通じた学び
本日は、生徒朝会が行われました。大きく二つの内容です。一つは、生徒会長のお話。
「4月は学年ごとの活動でしたが、徐々に学校全体での一体感が増してきました。そして、仲が良くなると行事や活動が成功するということが体育祭を通じて分かりました。玲瓏祭でも、学級、グループ、裏方のみんなで、一体になって活動をしていきましょう。」とのこと。さすがです。
そして、図書委員会より読書習慣に向けての呼び掛け。専門委員会ごとに分かれ、クイズに答えました。
作家の名前や、作品の名前など、生徒が考えた3択のクイズをそれぞれの縦割りのグループで話し合いながら楽しく答えていました。
こうした活動も小さなプロジェクトです。図書委員会の生徒は、発表に向けていろいろと考え、工夫をしていました。そこでは、必ず主体的な学びがあります。生徒会や学級活動等の特別活動は、こうしたプロジェクトを行いやすい場であり、その中で普段の様々な学習が生かされることになります。特に、コミュニケーション能力が実践的に高められます。今回の指導要領で、特別活動が重視されたのには、このような意図があります。今後も、発表等のプロジェクトを大切にしていきたいと思います。